コーダとは
コーダ(Children of Deaf Adults)とは、きこえない、または、きこえにくい親(以下、きこえない親)をもつきこえる子どものことを指します。1983年にアメリカで生まれた言葉で、日本には1994年に紹介されました。最近では映画やドラマの題材として取り上げられることも増えてきました。
国際組織である「コーダ・インターナショナル」では「コーダとは、きこえない親を一人以上もつ(きこえる)人」と定義されています。
このサイトでもそれに倣い、両親ともきこえなくても、どちらかの親だけがきこえなくても、また、親がろう者でも難聴者でも、きこえる子どもはみんなコーダとします。
はじめに
人は「これから、どうなっていくのか?」 先のことが分からないと不安になることがあります。
ある程度、先のことがわかっていれば、イメージすることができ、心の準備ができます。
このサイトでは、きこえない親をもつコーダには何が起こりうるのかということを、たくさんのコーダの語りを用いながら整理しました。
また、コーダの手記も掲載しています。ちょっと先ゆく先輩コーダが、何を思い、どんな人生を歩んできたのかを知る手段として活用してみてください。
そして、このサイトから、コーダに共通する大変さや、一方でコーダが持つ力強さをぜひ感じ取ってみてください。
コーダのみなさまと、そのお父さま・お母さまが、親子関係のことで、ふと不安を感じるとき、あるいは、広くみなさまがコーダのことを知りたいと思ってくださったときに、このサイトが、先の見通しをもつためのひとつの手掛かりとなれば嬉しく思います。
Profile

中津 真美 (Mami Nakatsu)
東京大学多様性包摂共創センター バリアフリー推進オフィス 特任講師
筑波大学大学院 人間総合科学研究科 生涯発達科専攻 博士課程修了
博士(生涯発達科学)
青少年を対象とした福祉・教育領域の現場勤務を経て、2005年に東京大学バリアフリー推進オフィス(前・バリアフリー支援室)に入職。障害のある学生・教職員への支援のほか、全学構成員へのバリアフリーに関する理解推進のための業務に従事している。
ろう者の父と、聴者の母をもつコーダであり、コーダの親子関係の心理社会的発達研究にも取り組む。
J-CODA(コーダの会)所属。専門領域は、聴覚障害学、障害者支援、障害者福祉、家族支援など。
| コーダという子どもたちのこと 金子書房 note |
| 今、社会の仕組みの中でCODAを考えるとき 読売新聞オンライン |
| 親と子の役割が逆転してしまうことも。聴こえない親を持つ子どもの困難、知ってますか? ハフポスト |
| 東京大学 バリアフリー推進オフィス IncluDE UTokyo Office for Disability Equity |
| 東京大学 多様性包摂共創センター IncluDE UTokyo Center for Coproduction of Inclusion |
コーダに関する主な論文・著書
論文
| 聴覚障害の親をもつ健聴児(Children of Deaf Adults:CODA)の通訳役割の実態と関連する要因の検討. AUDIOLOGY JAPAN.2020 |
| 聴覚障害の親をもつ聞こえる子どもの自助グループにおける取り組み. 社会福祉研究. 2020 |
| 聴覚障害の親をもつ健聴の子ども(CODA : Children of Deaf Adults)の通訳役割にもとづいた親子関係形成に関する研究動向. コミュニケーション障害学. 2016 |
| 聴覚障害の親をもつ健聴の子ども(CODA)における親からの心理的自立時期の長期化の要因. 音声言語医学. 2014 |
| 聴覚障害の親をもつ健聴の子ども(CODA)の通訳場面に抱く心理状態と変容. AUDIOLOGY JAPAN. 2013 |
| 聴覚障害者の親をもつ健聴の子ども(CODA)の通訳役割に関する親子の認識と変容. 音声言語医学. 2012 |
著書等
| 『コーダ 私たちの多様な語り:聞こえない親と聞こえる子どもとまわりの人々』 第6章 聞こえない親の看取り介護と向き合うとき(澁谷智子 編 生活書院2024) |
| 『コーダ きこえない親の通訳を担う子どもたち』 (単著・中津真美 金子書房2023) |
| 『現代思想2022年11月号 特集ヤングケアラー 家族主義的福祉・貧困の連鎖・子どもの権利・・・・・』 ヤングケアラーの中のコーダ――きこえない親をもつきこえる子どもの通訳の役割(青土社2022) |
| 『特集「コーダ」を考える 季刊みみ第186号(2024年冬季号)』 座談会 いま、コーダが伝えたいこと/コーダの健やかな未来を紡ぐために(全日本ろうあ連盟2024) |
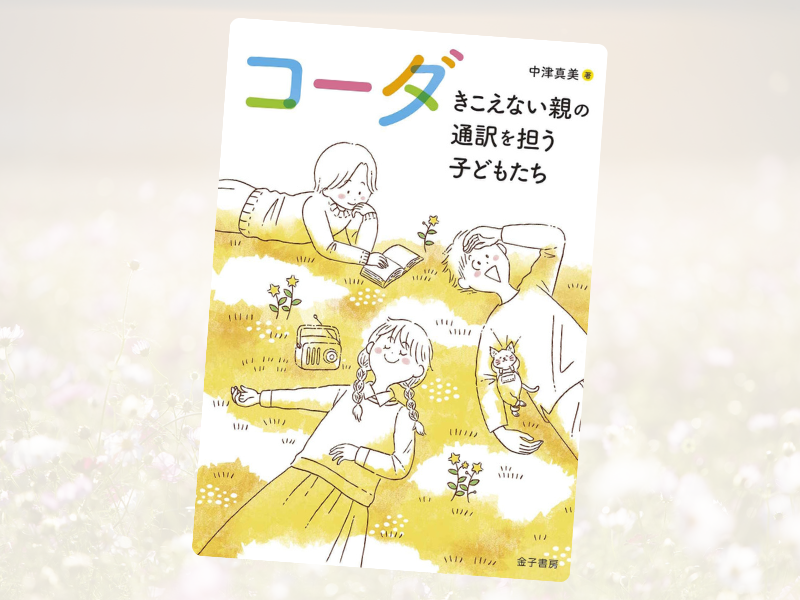
コーダ関連情報の書籍をまとめております。こちらのリンクからメディア関連情報の書籍一覧のページへジャンプします。



